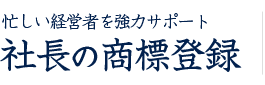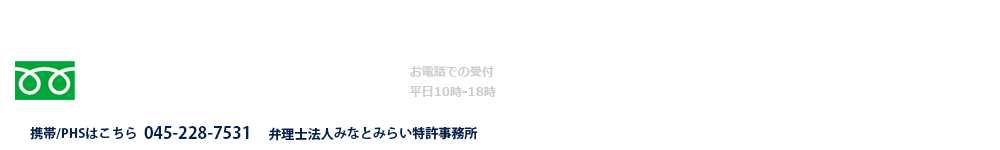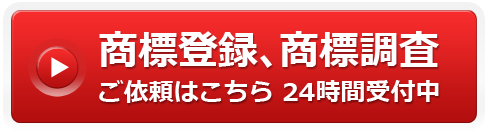実例から見る商標のライセンス契約(商標使用許諾契約)の概要と注意点

登録商標に関して、企業間でよく話題に上るのがビジネス上のライセンス契約です。
商標権は財産の一種と扱われており、譲渡や売買も可能です。権利としては自社で持ちつつも、他社にも一定の条件で使用を許可するといったこともできます。
これは世間一般でライセンス契約と言われているものであり、代理店ビジネス、フランチャイズビジネスなどで広く使われています。
目次
- 登録商標の「ライセンス契約(使用許諾契約)」とは
- ライセンス契約のメリットとデメリット
- ライセンス料金のロイヤリティ比率
- ライセンス契約の留意点
- リッツ、オレオはライセンス商品
- 商標のライセンス契約をめぐるトラブル
- 事業継続のためにはオリジナルブランドの育成も
登録商標の「ライセンス契約(使用許諾契約)」とは
自社商品(サービス)の商標が無事登録となると、次のステップとしてその商標をいかにうまくビジネスに活かしていくかという課題が生まれます。他社にとられたくない商標を自社で念のため抑えておく、という企業戦略上の商標登録というパターンもあるでしょう。
しかしながら、商標登録を取得し権利を所有し続けるには、出願から登録の継続更新まで無視できないほどの経費がかかります。登録商標を使って自社商品の販売促進に全力を尽くすことは言うまでもないことですが、商標を自社の「知的財産」としてもっと幅広く利用する方法があります。
それが「登録商標のライセンス契約」です。「登録商標のライセンス契約」とは、つまり「商標使用許諾契約」のことで、自社の商標を他社に使用させる見返りとしてその使用手数料を受領するという商取引契約を意味します。
商標のライセンス契約については、特に法律の定めなどはなく、契約を締結する両者が合意すればどのような内容であっても構いません。とはいっても、長年培われてきたビジネス社会の「慣習」と「相場」いうものがあります。
またライセンス契約には、商標権を保有する企業(ライセンサー)にとっては早期に広い範囲でブランド展開ができるメリットがありますし、商標の使用権を得た企業(ライセンシー)にとっても商標が持つブランド力・信用力をもとにビジネス展開することができるのです。
ライセンス契約のメリットとデメリット
飲食業界を例にすると分かりやすいと思いますが、おしゃれなことで知られているA社という喫茶店があるとします。A社は自社のブランドを広げるために店舗網の拡充を考えていますが、全て直営店舗とするのはリスクが高いところです。一方、B社では、新たに喫茶店を始めようと考えていますが、知名度ゼロの状態から顧客を開拓するのにハードルを感じているところです。
商標は、このような2社について、双方にメリットのある形で結ぶことができるのです。A社側で自社の店舗名(商標)について、B社に使用許可を出せば良いのです。こうすることによって、A社としてはリスクの低い形で自社のブランド名を冠する店舗を増やすことができますし、B社にとっても最初から消費者の認知度の高い状態で喫茶店を始めることができます。これがライセンス契約のメリットです。
ライセンス料金のロイヤリティ比率
まずは「ライセンス料金の算出方法」ですが、これは「通常使用権」が売上の3%~5%、「専用使用権」が10%というのが算出比率の相場といわれており、使用者が権利者に支払うライセンス料金のことを「ロイヤリティ」と呼びます。
もちろん、当然ながら商標自体の「商品価値」によってこの比率にも幅が出てきます。売上アップが確実に見込める商標であれば、売上比率は相場どおりとして、契約締結時の頭金としてまとめた金額を支払う、というパターンもあります。
ちなみに随時継続的に発生する使用料を「ランニング・ロイヤリティ」、頭金のことを「イニシャル・ロイヤリティ」と呼ばれています。近年は、特にベンチャー企業を中心に、商標や特許あるいは著作権使用料を全般的に「ライセンス・フィー」と表現することも増えてきていますが、言葉の意味は「ロイヤリティ」と同じです。
ライセンス契約の留意点
ブランド展開、新規事業の開始にあたってメリットが大きいライセンス契約ですが、当然ながら欠点がひとつもないわけではありません。それは、ライセンス契約は、お互いの利害関係が一致することを条件がなければ成立し得ないという点です。
先ほどの喫茶店の例ですが、お互いの営業エリアが被らないうちはwin-winの関係を維持できますが、例えば、A社の財務基盤が強化され、直営店舗路線に舵を切った場合、どのようなことが起きるでしょうか。どのように転んでも、B社にとっては良い結果にはならないのは明確です。
つまるところ、ライセンシーの立場は不動のものではないということなのです。このところ話題になっているヤマザキナビスコのリッツ、オレオの販売終了も元をたどれば、商標のライセンス契約に行き着きます。
リッツ、オレオはライセンス商品
今ではヤマザキナビスコの看板商品と認識されているリッツ、オレオですが、実はこれらはアメリカのナビスコ社が開発したものであり、日本のヤマザキナビスコはライセンス契約を締結して製造・販売していたのです。
ヤマザキナビスコはライセンス契約に基づいて、リッツ、オレオを製造・販売してきましたが、このライセンス契約は2016年8月末で期限を迎え、更新せずに終了することになりました。ヤマザキナビスコはリッツ、オレオの販売を終了せざるを得なくなったのです。
なぜ、このような事態に陥ったかというと、ナビスコ社の親会社であるモンデリーズが日本法人を通じて直接販売するビジネスモデルに転換したのが大きいです。リッツ、オレオの商標権を保有しているのは、あくまでモンデリーズですから、ヤマザキナビスコはこの方針に従わざるを得ないのです。
商標のライセンス契約をめぐるトラブル
商標のライセンス契約については、不動産賃貸契約などとは異なる「知的財産権」に関わる案件だけに、契約する企業同士が不慣れな場合には、契約後に予期せぬトラブルが生じ、交渉がこじれると裁判沙汰に発展してしまうというパターンも少なからず見受けられ、その中には以外にも有名企業も含まれている場合もあります。
最近の実例としては、有名な「うがい薬」をめぐる商標トラブルがありました。これは、日本の(株)明治と米国の製薬会社「ムンディーファーマ」とのうがい薬「イソジン」とそのマスコットキャラクターである「カバくん」における係争です。
明治はムンディーファーマと「イソジン」の日本における製造・販売についてのライセンス契約を1961年から長く締結していましたが、2016年にこの契約を終了させ、新たに「シオノギ製薬」と契約することを選択しました。そして明治は独自に自社ブランドのうがい薬を商品化することとなったのですが、ここで問題となったのはそれまでの「イソジン」の瓶ラベルにあしらわれていたイラストの「カバくん親子」です。
長く親しまれていたキャラクターということで明治は急遽この「カバくん」を商標出願したのですが、シオノギのイソジンの方も「カバくん」に似たキャラクターを使って販売を始めたため、明治はこれを「不正競争防止法」違反として販売差止の仮処分請求を起こしたのです。
このトラブルは、結局シオノギ側が折れてキャラクターの図案を変更することで和解が成立しましたが、明治がもっと早く「カバくん」の商標を登録しておけば、このようなトラブルは避けられたはずいです。ライセンス契約時の商標登録の重要性について示唆に富んだ事案といえるでしょう。
事業継続のためにはオリジナルブランドの育成も
ライセンス契約は、ライセンサー、ライセンシーの双方にとってメリットのあるビジネスモデルですが、ライセンシー側においては、使用許諾を得た商標のブランド力に頼りきりになるのではなく、常にその先を考えておく必要があります。
ヤマザキナビスコはリッツ、オレオといった看板商品を失うという痛手にはあいましたが、自社開発したブランド商品も数多くあるため、会社の屋台骨が揺らぐという事態は避けられました。今後は、社名をヤマザキビスケットに変更して、海外事業にも取り組んでいくとのことです。企業としての持続、事業継続を図っていくためには、自社のオリジナルブランドの育成が不可欠ということでしょう。