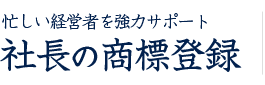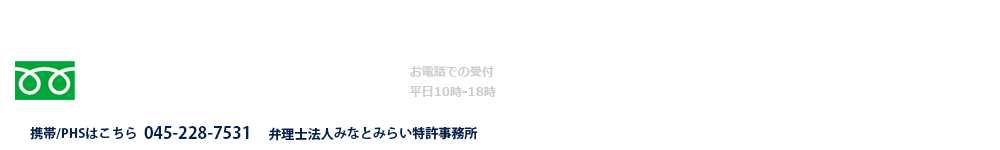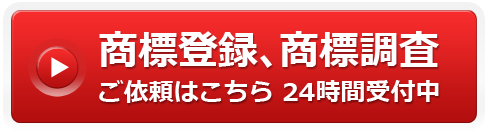商標法が定める区分と指定商品・指定役務
「1区分1業種」の原則
商標とは、商品に付与する文字や記号またはマークなどの識別標章であり、その商標が付けられた商品やサービスの種類は多岐にわたっています。そして、特許庁から許諾査定を受け登録された商標は、10年毎の更新手続きを続ける限り、半永久的に権利を所有できます。
商標が永久権といってもよいほどの効力を有する権利であるだけに、その権利は商標が付与された商品(サービス)の分野のみに限定される必要があります。そこで商標法では出願された商標に対し、その分野を細かく45種類に分類して区分されています。
商標法で定められている区分とは「1業種1区分」となっているため、たとえばある商標を菓子と文具の両方で取得したい場合は、2区分両方での商標出願が必要となり、1区分の出願費用が加算されます。
ただし、これが菓子とパンであった場合には両者は同じ業種として1区分に分類されているため、出願費用は加算されません。つまり、「区分」イコール「業種」ととらえてもよいでしょう。
3つの拒絶理由
現在、特許庁が規定している42種類の区分にはそれぞれの業種の商品やサービスの名称が細かく指定されており、それらは「指定商品」「指定役務」と呼ばれています。原則として、商標が認められる商品(サービス)は、各区分にある「指定商品」「指定役務」に限定されることになっています。
現在の日本で出願された商標のうち、拒絶理由通知を受けたものを分析してみると、下記の項目が多いことが分かります。
(1) 区分を誤認しているものや商品・役務を指定していないもの
(2) 指定範囲が明確でないもの
(3) 使用または使用予定の確認を要するもの
以上の3項目が、拒絶理由のなんと約半数を占めているといわれています。
注意すべき「区分」「指定商品」「指定役務」
(1)区分を誤認しているものや商品・役務を指定していないもの
たとえば「第21類 歯磨き」と指定してしまった場合はどうでしょうか?第21類は「家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品」となっているので間違いやすいのですが、「歯磨き」は第3類の「洗浄剤及び化粧品」の指定商品と規定されているので、このままでは拒絶査定となってしまいます。商標を取得しようとする商品が第何類に属しているかを丁寧に調べておく必要があるのです。
(2) 指定範囲が明確でないもの
たとえばある事務用品の商標を出願する際に、区分内の商品をできるだけ多く抑えておきたいということで「第16類 全ての商品」と指定したとします。
しかしながら、各区分に属する商品は特許庁が例示公表しているものの他にも数多くあることから、これではどの商品について商標を取得したいのか判然としないため、拒絶査定を受けてしまいます。したがって、この場合は商品名を明確に記載しておくことが必要で、闇雲に広範囲の権利を確保しておこうという目論見は通用しないということになります。
(3) 使用または使用予定の確認を要するもの
商標法では出願された商標を出願人が使用しているか、あるいは使用する予定があるのかが査定の基準となっています。したがって、指定商品または指定役務が1区分内の広範囲に及ぶ場合、実際に使用されているかまたは使用予定が判然とするカタログやパンレットなどの資料の提出を特許庁から求められる場合があるのです。この要求に応じられない場合は拒絶査定となるので注意が必要です。
これは「とりあえずヒット商品になりそうなネーミングの権利をとっておこう」という俗に「商標ブローカー」と呼ばれる行為を防ぐことも目的のひとつといわれています。
なお、特許庁が確認を求める場合の目安として、互いに類似した商品(役務)が8個以上となる場合とされています。
これら拒絶査定を受けた商標出願の大半は、商標法が定める区分と指定商品・指定役務を事前に掌握しておくことで拒絶を回避できたものが多く含まれることを考慮すれば、これらの規定を十分に把握しておくことの重要性がよく分かるでしょう。 タイムロスを回避するためにも専門家にまずは相談する事をオススメします。