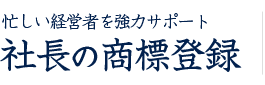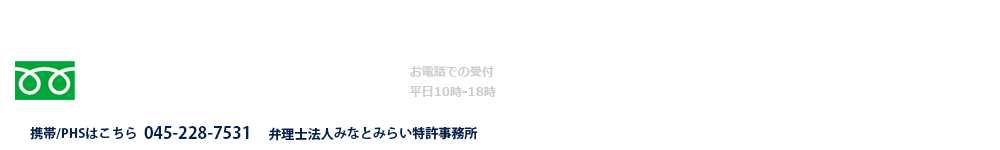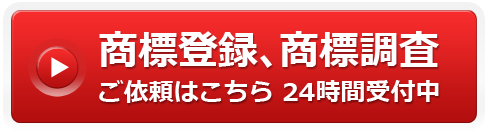商標審決取消訴訟の実際とその内容
拒絶査定を覆すための審判制度
商標出願が拒絶査定を受けた場合は、出願人のほとんどは登録商標をあきらめることとなります。しかしながら、拒絶された査定理由がどうしても承服できないというときは拒絶査定後3ヵ月以内に出願人は特許庁に対して異議申立てをすることができ、この制度を「拒絶査定不服審判」といいます。そしてこの審判にて審理が行われ下された判断が「審決」と呼称されます。つまり、拒絶査定通知を受け取ってもあきらめずに拒絶査定不服審判を申し出ることによって商標登録が認められる場合もあるのです。
日本においては、2015年の時点で拒絶査定のうち約2割が不服審判となっており、そのうちの約4割が商標登録となっています。つまり拒絶査定全体では約1割足らずではありますが、不服審判の半数近くが晴れて商標登録となっているというのが現状です。ちなみに、審判は3名~5名の特許庁審査官による合議制で行われています。近年、特許に関しては審決での登録率は下降気味ですが、商標に関しては登録率が上昇している傾向にあります。
知財裁判所へ訴える「審決取消訴訟」
それでは、拒絶査定不服審判にて下された審決は原則として特許庁の最終判断となり、出願人側にとっては不幸にして拒絶が有効との審決(商標登録不認可)となった場合は、これで本当にあきらめるしかないのでしょうか?このような場合に利用できる制度が「審決取消訴訟」で、知的所有権関連を専門的に審議する「知的財産高等裁判所」に提訴することができます。特許庁が下した審決に異議を申し立てて今度は裁判官の判断に委ね審決を取消す採決を求め訴状を提出するというわけです。
著作権などを含む特許や商標などの知的所有権の分野は極めて専門性が高いために、一般の裁判所ではなく2005年に設立された知的財産高等裁判所が取り扱うようになっているのです。審決取消訴訟が一般の民事裁判と大きく異なる特性として、弁護士以外に弁理士が原告の代理人として認められている点が挙げられます。ちなみに、審決取消訴訟に関しては東京高等裁判所の専属直轄事案であることが特許法で定められており、知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別支部なのです。
審決取消訴訟では、まず裁判官が訴状をチェックし書類不備があれば原告(出願人)に書類の補正命令を出します。訴状に不備がなければ通常の裁判と同様に口頭弁論の日時が原告と被告(特許庁)に通達され、原告側は取消事由の主張を具体的に述べた第1回の準備書面を用意して裁判がスタートします。
判例を参考とする必要性
審決取消訴訟においても、原則として判事が下す判決によって裁判が終了しますが、普通の民事裁判と同様に判事が原告に対し訴えの取り下げを勧告し裁判を終結させる場合もあります。そして原告の訴えを棄却する判決であった場合には判決送達日から2週間以内に最高裁判所への上告を行うことが可能となっており、これが最終の司法判断ということになります。
このように、商標をめぐる司法判断については特許庁の審決が一般民事裁判の一審にあたり、知的財産高等裁判所での審議が二審に該当し、最後が最高裁という特別な三審制度が敷かれているといってよいでしょう。近年の商標制度は改定が進み、立体・色・音・動きなどこれまでは想定外であった新しい概念の商標が誕生してきています。これによって、商標の拒絶査定不服審判や審決取消訴訟が増加することが予想され、判例が積み重なっていくことで登録商標の判断基準が形成されていくことでしょう。
商標登録を企業戦略上の重要事案を位置付けている企業においては、単に商標出願を乱発するのではなく、より効率よく登録させるために、過去の判例などを入念に調査して参考とする必要性があることはいうまでもありません。